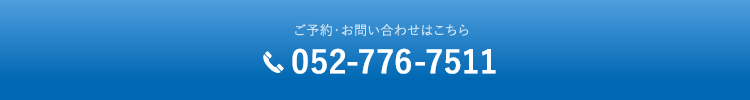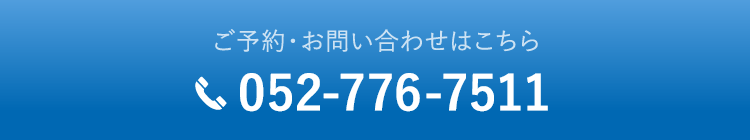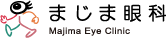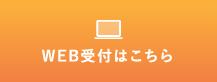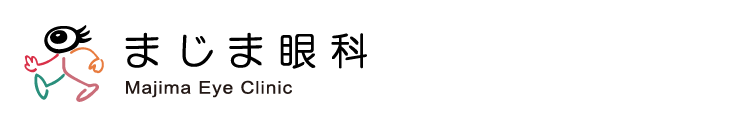

HISTORY
まじま眼科の歴史


清眼僧都(せいげんそうず)というお坊さまは夢の中で異国人からある医書を示された。そうして手にした医書(おそらく中国の眼科書であったと思われる)をもとに、眼科を始めたのが、日本で最も古い歴史をもつ馬島流眼科であると言われ、以来、尾張国海東郡馬島村(現在の愛知県海部郡大治町)の医王山薬師寺・蔵南坊の住職は代々、眼科医として活躍した。13代目にあたる慶法院は寛永9年(1632年)、後水尾天皇の息女、三の宮の眼病を治療し、「明眼院(みょうげんいん)」の寺号を賜った。天保の頃にはいくつもの病棟をもつほど、栄えたが、明治以降、僧職と医師の兼職が禁止となり、明眼院の診療所は閉鎖され寂れていったが、戦後、「明眼院」は現在の海部郡大治町に再興され、眼科発祥の地として注目を浴びた。

一方、明治以降、明眼院を後にした馬嶋流眼科を発症とする馬嶋家は、後世にその流れを継承し、現代の白内障手術の先駆者として知られる第37代馬嶋慶直(藤田学園名古屋保健衛生大学学長)、38代馬嶋清如(同眼科学教授)へと引き継がれ、優れた研究者、臨床医として活躍している。
当院は、その血縁筋である故馬嶋季彦により、戦後、地域に密着した医療を目指し、開業。長い馬嶋流眼科の歴史を背景に、常に時代に即した眼科医療機関として、いつの時代も変わらず患者様の立場に立った、人に寄り添う暖かい眼科でありたいと願っている。
HISTORY
まじま眼科の歴史


清眼僧都(せいげんそうず)というお坊さまは夢の中で異国人からある医書を示された。そうして手にした医書(おそらく中国の眼科書であったと思われる)をもとに、眼科を始めたのが、日本で最も古い歴史をもつ馬島流眼科であると言われ、以来、尾張国海東郡馬島村(現在の愛知県海部郡大治町)の医王山薬師寺・蔵南坊の住職は代々、眼科医として活躍した。13代目にあたる慶法院は寛永9年(1632年)、後水尾天皇の息女、三の宮の眼病を治療し、「明眼院(みょうげんいん)」の寺号を賜った。天保の頃にはいくつもの病棟をもつほど、栄えたが、明治以降、僧職と医師の兼職が禁止となり、明眼院の診療所は閉鎖され寂れていったが、戦後、「明眼院」は現在の海部郡大治町に再興され、眼科発祥の地として注目を浴びた。

一方、明治以降、明眼院を後にした馬嶋流眼科を発症とする馬嶋家は、後世にその流れを継承し、現代の白内障手術の先駆者として知られる第37代馬嶋慶直(藤田学園名古屋保健衛生大学学長)、38代馬嶋清如(同眼科学教授)へと引き継がれ、優れた研究者、臨床医として活躍している。
当院は、その血縁筋である故馬嶋季彦により、戦後、地域に密着した医療を目指し、開業。長い馬嶋流眼科の歴史を背景に、常に時代に即した眼科医療機関として、いつの時代も変わらず患者様の立場に立った、人に寄り添う暖かい眼科でありたいと願っている。
EQUIPMENT
設備紹介

まじま眼科入口

受付

診察室

視力検査評

視野検査

処置室

検査機器

視力回復訓練

装用指導
HOSPITAL INFORMATION
病院概要
| 病院名 | まじま眼科 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区藤が丘141番地 (藤が丘駅前ビル2F) |
| 電話 | 052-776-7511 |
| 開設 | 平成8年 |
|---|---|
| 院長 | 杉野太郎 |
| 診療科目 | 眼科一般 |
ACCESS
アクセス
〒465-0032
愛知県名古屋市名東区藤が丘141
藤が丘駅前ビル2F
●地下鉄東山線「藤が丘」駅2番出口すぐ
●市バスターミナル前 藤が丘駅前ビル 愛知銀行2F